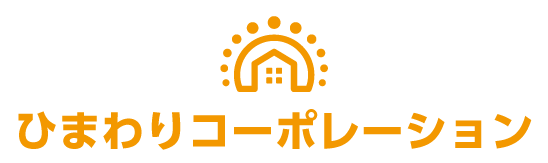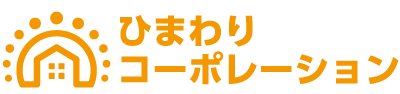家族葬・火葬・一日葬などについて基本的な質問に回答
Q&A
コロナ対策として取り組んでいる対応についても解説しています
これまでご遺族様の心に寄り添いながら葬儀サービスに携わる中、世田谷近郊エリアの皆様からサービスに関するご質問・コロナ対策に関するご質問をお寄せいただいておりますので、主な内容をまとめて掲示しております。
サービスに関する補足的なマニュアルとしてご利用いただけるよう、端的に質問・回答形式で分かりやすく説明しておりますのでぜひご覧ください。今後葬祭サービスをご利用の際にご参考にしていただける内容となっております。
FAQ
よくある質問
葬儀費用について
- 追加料金はありませんか?
- 公営火葬場や公営斎場がある地域では、追加料金はありません。
ただし、火葬式【たんぽぽ】につきましては、公営火葬場がない一部の地域では火葬料金を追加でお支払いいただくことになります。一日葬【すずらん】、家族葬【こすもす】につきましては公営斎場がない一部の地域では、式場使用料を追加でお支払いいいただくことになります。
その場合、式場使用料を5万円まで当社が負担いたします。
火葬場や斎場によって料金が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 希望の葬儀場があるのですが、対応できますか?
- お客様のご希望の葬儀場をできる限りご案内させていただきます。
地域や時期により数日待ちというケースもありますので、その場合はなるべくお客様のご意向に沿った別の葬儀場をご案内させていただきます。
- 費用を抑える方法はありますか?
- ご自宅でご葬儀を行えば、式場の使用料がかかりません。公営斎場は民営斎場に比べて使用料が安価です。また、斎場に火葬場が併設されていれば、火葬場までの移動に使用する霊柩車やマイクロバスなどが不要になります。
私たちは、費用を抑えたいというご家族にはまず、火葬場を併設した公営の葬儀場をご案内いたします。
火葬式について
- 火葬式とはどんなお葬式ですか?
- お通夜や告別式を行わず、火葬前に短い時間でお別れをするのが火葬式です。
亡くなってから24時間経過しないと火葬はできませんので、亡くなった次の日以降に行われます。
- 火葬式はどこで式を行うのですか?
- 安置施設、もしくはご自宅から出棺し、火葬場でお別れのセレモニーを執り行うのが一般的です。葬儀場を借りる場合もありますが、葬儀場使用料が発生します。
- 戒名をいただきたいのですが、火葬式でも戒名をいただくことができますか?
- もちろん可能です。火葬式は、ご僧侶に読経いただくこともできますし、読経はしないで、戒名だけいただくこともできます。
- 菩提寺があっても火葬式はできますか?
- 菩提寺の許可をいただく必要がありますので、火葬式をする前にご僧侶と相談をしてください。
- 火葬式での食事はどうするのですか?
- 火葬式はお通夜・告別式がないので、お通夜後に召し上がっていただくお清めはご用意いたしません。
火葬中での精進落としをご希望のご家族には、火葬場の控え室にお食事をご用意いたしますが、できない場合もあります。
一日葬について
- 一日葬とはどんなお葬式ですか?
- お通夜は行わず、告別式の1日だけでお別れいただくお葬式です。従来のお通夜・告別式2日間のお葬式に比べて、高齢の方でもお疲れを感じられることがなく、ご会葬される皆様のご都合も合わせやすいお別れです。ご葬儀の費用を抑えられることも特徴のひとつです。
- 2日間の葬儀に比べて、どんな費用が抑えられるのですか?
- お通夜がないので、お清め(お食事)の費用がかかりません。私たちにご僧侶や神主様の手配をご依頼された場合は、お布施や祭祀料とお車代、ご膳料1日分を抑えることもできます。また、遠方からのご会葬者がいらっしゃる場合は、宿泊代も抑えられます。
式場によっては、利用料金が半額になることもありますが、ほとんどの場合は、お通夜がなくても前日から設営で使用するので、通常料金となります。
- 一日葬はどんな宗教でも行うことができますか?
- 対応可能です。
ただし、お付き合いのある宗教者様(菩提寺様など)がいらっしゃる場合は、菩提寺の許可をいただく必要がありますので、一日葬をする前にご僧侶と相談してください。
- 一日葬でも、斎場に泊まって故人といっしょに過ごすことはできますか?
- 前日からご葬儀の準備で斎場を使用するため、宿泊可能な斎場であれば故人様と一晩お過ごしいただけます。宿泊できない斎場であっても、準備をしている間はご親族や近しいご友人だけで、お別れのお時間をゆっくりお過ごしいただけます。
家族葬について
- 家族葬とは何ですか?
- 家族葬は、勤務先の関係者や近隣の方々などの会葬をお断りし、親族や親しい方など、ごく近しい方々で故人様をお見送りいたします。
家族葬と呼ばれていますが、あくまでも「ご家族を中心にしたご葬儀」という意味で、ご家族はご会葬者をお選びいただき、人数を限定することができます。家族葬は、勤務先の関係者や近隣の方々などの会葬をお断りし、親族や親しい方など、ごく近しい方々で故人様をお見送りいたします。
家族葬と呼ばれていますが、あくまでも「ご家族を中心にしたご葬儀」という意味で、ご家族はご会葬者をお選びいただき、人数を限定することができます。
- 家族葬と密葬は違うのですか?
- 親族だけで執り行われるご葬儀を、従来は「密葬」と呼び、多くの場合はお別れの後に火葬し、後日改めてお別れ会などを行うものでした。
一方、1990年代に登場した「家族葬」は、親族や親しい方など喪主様がご会葬者を限定し、通夜・告別式を執り行った後に火葬するものです。
- 家族葬のメリットはなんですか?
- 家族葬には大きく2つのメリットがあります。1つ目は、費用を抑えられることです。ご会葬者が親族や親しい型など少人数で規模も大きくないので、司会や運営スタッフ、大型の式場が不要なケースが多くみられます人数が少なければ少ないほど、お通夜や告別式での飲食代、返礼費用も抑えることができます。
2つ目は故人様とゆっくりお別れいただけることです。ご会葬者は親族や親しい方だけなので、弔問や挨拶などに時間を取られることなく、故人様への愛情や感謝をしっかりとお伝えいただけます。
- 家族葬のデメリットはなんですか?
- 親族や親しい方だけでご葬儀を執り行うため、参列できなかった方々から、「連絡してほしかった」「お世になった人だから、お焼香をあげたかった」と言われる場合があります。
また、ご葬儀後に故人様が旅立たれたことを知った方々には、その都度旅立たれた経緯を説明し、弔問への対応が必要になります。また、お香典が少ないため、自己負担費用が大きくなります。
- 家族葬にしたいので、亡くなったことを近所の方に知られずにできますか?
- 病院など自宅以外で亡くなられた場合、一般的には一度ご自宅にお戻りいただきます。
しかし、病院などから安置施設へ直接ご安置すれば、ご近所の方に知られることはありません。
- 家族葬で香典や供花を、いただいてもよろしいのでしょうか?
- 多くのご家族はいただいていらっしゃいます。ご辞退を希望される際は、事前にお電話もしくはFAXでお伝えするようにいたします。
お断りしたにもかかわらず、ご会葬者が「どうしても」と置いていかれたご香典に対してはお返しをし、故人様に代わって感謝の意を示しましょう。また、ご弔電やご供花が届いた場合も、お礼を申し上げましょう。
無宗教葬について
- 無宗教葬ってどんな葬儀なのでしょうか?
- 仏式、神式、キリスト教などの宗教によらないお葬式です。
僧侶による読経のかわりに、音楽を流したり、献花をするなどして故人を偲びます。
式次第に決まりはないので、故人らしいお葬式を創ることができますが、菩提寺やご親戚などと話し合っていただく必要があります。
- 無宗教葬では、どんな儀式をするのでしょうか?
- 代表的な儀式は献花と呼ばれる、お花を供える儀式です。
仏教では、お経やお焼香がありますが、無宗教では決まりがありませんので、ご家族と打合せをしながら儀式の内容を決定します。
- 無宗教葬はどのような流れで進行するのでしょうか?
- 無宗教葬に決まった流れはありません。お経やお焼香といった宗教の儀礼がないからです。献花やお柩を囲んでのお食事など、ご家族様がご希望される内容を伺いながら、一緒に進行をお考えいたします。
ひと昔前であれば、伝統を重んじる方などに反対されるケースもあったようですが、最近はほとんどありません。親しい方だけを呼ぶ家族葬の増加など、お葬式への考え方が大きく変わっているのも要因です。
- 音楽葬はできますか?
- はい、承っております。音楽葬は、無宗教葬の中でも最近増えているご葬儀のスタイルです。故人様が生前お好きだった音楽を中心としたご葬儀を「音楽葬」と呼びます。
録音された音源をCDでお流しするほか、ピアノや弦楽四重奏などの生演奏による「献曲」、合唱による「献歌」、または音楽を聴きながら軽食でおもてなしをする「ティーセレモニー」など、自由な形式で執り行うことができます。無料の事前相談で、音楽葬に適した式場や式次第をご提案させていただきます。
- 菩提寺がありますが、無宗教葬をすることはできますか?
- ご住職と相談する必要があります。代替え案として、仏教儀式の前後のお時間(お通夜のお経の後など)に無宗教葬を取り入れる方法もあります。
- 納骨(お墓)は、どのようにするのですか?
- 霊園や納骨堂、永代供養墓など、納骨は従来と同じ形式となります。
最近では、散骨や樹木の下に収める樹木葬にする方もいらっしゃいます。
- 無宗教葬をした後の四十九日法要や仏壇などはどうすればいいのですか?
- 無宗教なので特に決まりはありませんが、四十九日、一周忌など定期的に供養の場を設けることをお勧めしております。仏教のように集まってお経をあげるような儀式はありませんが、皆様でお食事を召し上がりながら、旅立他偲ばれてはいかがでしょうか。
仏教でいう仏壇、位牌についても、無宗教では決まったものはありません。旅立たれた方を偲ぶお品として、ご遺灰の一部をお納めするデザイン性の高いミニ骨壷やペンダントなどがございますので、よろしければご紹介いたします。
喪服(着物)について
- 着付けは頼めますか?
- 着付け・ブロー・ヘアセットを承ります。それぞれ施術時間は30分くらいです。
お声掛けいただければ専門のスタッフを手配致します。
- レンタル衣装の家紋はどうなっていますか?
- 一般的な紋と言われる「五三の桐」が入っています。
お貸出しする衣裳によって多少異なりますのでご了承ください。
- 夏用の着物を着る時期は決まっているの?
- 正式には、7月・8月です。
10月~5月は「袷(あわせ)」と言われる裏地の付いた着物。
6月・9月は裏地のない「単衣(ひとえ)」の着物。
7月・8月は絽(ろ)や紗(しゃ)など透けるような素材で作られた「うすもの」の着物を着用するのがマナーです。
近年では6月~9月を絽の着物で通すことも多いので、ひなたでは夏用に絽の着物をご用意しております。
- 着物は通夜と告別式の2日間着なくてはいけないのでしょうか?
- どちらか1日でも結構です。とくに告別式だけ着物をお召しになる方が多いようです。
着付けスタッフがよく話すのですが、悲しみに沈んでいればいるほどうつむき気味で猫背になるご遺族が多いそうです。
しかし長じゅばんから着物、帯と着付けが進んでいくうちにだんだんと姿勢が正されていき、着付けが終わるころにはビシッと背筋が伸びて気持ちまでまっすぐに変わっていくのが分かるそうです。大切な方の最後をきちんと送るための準備の一つなんですね。
斎場について
- お葬式をする場所は主にどこがあるのですか?
- ご自宅以外では、自治体が運営する公営斎場、民間企業が運営する民営斎場や葬儀専用会館、寺院、集会場があります。
- 斎場を選ぶポイントを教えてください。
- 主なポイントは、
・ご自宅の近く、もしくはご会葬者の方が多い地域にあるか
・予想されるご会葬者の人数に対応できるか
・使用料が予算に見合っているか
の3つになります。
- 斎場の予約はどうすればいいのですか?
- 私たちが予約の手配をいたします。ご利用される斎場が決まっている場合は、空き状況の確認と同時に、斎場の使用料を含んだご葬儀のお見積りを作成いたします。ご利用される斎場が決まっていない場合は、「自宅から近い場所にある」「家族葬に相応しいところと」といったご希望をお聞かせください。ご家族のご希望に合った斎場を紹介いたします。
- 公営の斎場は誰でも利用できるのですか?
- 公営斎場を運営する自治体に喪主様がお住まいの場合など、葬儀場によってご利用対象者が決まっております。また、ご親戚の中にご利用対象者がいる場合、利用できる場合もございます。斎場にお尋ねいただくか、私たちにお問合せいただき、ご確認ください。
- お通夜の際、斎場で宿泊はできますか?
- 斎場によってはご宿泊できないこともあります。お通夜のお付き添いをご希望のご家族様には、宿泊可能な斎場をご案内いたします。なお、宿泊可能な斎場であっても、シャワーがついておらず、仮眠スペースに近い場合があります。また、斎場によっては、お泊りいただけますが、定められた時間以降の出入が制限されるところもあります。
- 宗派が違うお寺様の会館も利用できますか?
- お寺の会館の多くは、異なる宗派のご葬儀を行うことができます。行えない場合は、ご家族のご希望に合った葬儀場をご紹介いたします。
- 友引の日に斎場でお葬式はできないのですか?
- 多くの斎場は友引を定休日にしていますが、開場している斎場もあります。東京都の公営斎場では臨海斎場が、横浜市の公営斎場は4つある斎場のうちいずれかが持ち回りで開場しています。
友引とは本来は「共引」と書き、「共に引きあって勝負なし」という意味でした。それがいつの頃からか、「友を引く」という解釈が生まれ、友引のご葬儀が避けられるようになりました。友引を気にされる方もいらっしゃいますので、ご相談の上お決めください。
- 斎場を利用する際の住民料金とは何ですか?
- 公営斎場を運営する市区町村に、故人様や利用を申し込まれる方がお住いの場合に適用される利用料金です。市区町村外にお住まいの方が利用される場合に比べ、低料金に設定されています。斎場によって、住民料金が適用される条件が異なる場合がありますので、私たちがご案内いたします。
- 教会以外でもキリスト教葬はできますか?
- ご葬儀をたのまれる牧師や神父の承諾が必要です。キリスト教葬を執り行うことができる斎場をご紹介いたしますので、ご葬儀を行われる場所や会葬者の人数など、ご家族様のご要望をお伝えください。
- 自宅で葬儀をするメリットを教えてください。
- まず、式場使用料が不要であることが分かりやすいメリットです。また、葬儀という不慣れな儀式なので、住み慣れた場所で行うことで、精神面にも良い影響はあると考えることができます。
- 自宅で葬儀をするデメリットを教えてください。
- 葬儀用に設計されていないので、受付、会計、待合所、食事の場所などが少なく、天候・気温の影響も受けやすいことがデメリットです。対処方法として、状況に応じて、テントを設置したり、冬場はストーブを用意する方法があります。
- 自宅が葬儀で使用できないことはありますか?
- ほとんどありません。棺をご自宅へ入れることができればご葬儀はできます。ご葬儀の規模などによっては適さない場所もございますが、まずはご相談ください。
- 集会所が葬儀で使用できないことはありますか?
- 事前に確認しておくことをお勧めします。
集会所を葬儀で利用する際は、窓口をしている責任者の方へ申し込みます。マンションなど集合住宅では、管理人さんに申し込みをします。利用料金も含めて、事前に申込み窓口を確認しておくことをお勧めします。
- 集会所で葬儀をするメリットを教えてください。
- 使用料が一般的な式場より安価なこと、家から近いことが代表的なメリットです。
- 集会所で葬儀をするデメリットを教えてください。
- 葬儀用に設計されていないので、受付、会計、待合所、食事の場所などが少なく、天候・気温の影響も受けやすいことがデメリットです。
対処方法として、状況に応じて、テントを設置したり、冬場はストーブを用意する方法があります。
ご安置について
- 故人の安置をお願いする場合はどうすればよいですか?
- 葬儀社が病院(警察)へ、寝台車で故人様をお迎えにあがります。
その際、ご安置場所をどこにするか決めておかれることをおすすめします。ご安置場所については、ご自宅か、ご自宅以外にするかを決めていただけるとスムーズです。
ご自宅でご安置する場合、お布団(ベット可)と枕と掛布団をご用意ください。枕飾りなどの供養道具は用意いたします。また、ご自宅以外をお考えの場合はお気軽にご相談ください。お客様のご希望に沿った場所をご提案いたします。
- 自宅以外の安置場所はどこがあるのですか?
- 一般的な安置場所は、専門安置所・葬儀会館・寺院(自宅)などです。
従来はご自宅へ戻ることが一般的でしたが、最近は住宅事情により、ご自宅に戻らないケースが多くなっております。
ご自宅安置をご希望で、マンションやご自宅に階段がある方でも、ご相談ください。
- 安置している間、故人と会えますか?また付き添うことは可能ですか?
- ご安置の際もご面会していただけます。
ただ、ご安置場所によりお時間の制限や予約が必要なこともございます。また、付き添いの可否も、ご安置場所により異なりますので、お気軽にお問合せください。
- 自宅に安置する際の注意事項は?
- 季節を問わず、ご安置はエアコンのある部屋をおすすめいたします。ご弔問の方が多い場合は、お招きしやすい場所を選びます。ご自宅がマンションでエレベーターを利用される場合は、エレベーター室を広くするためにトランクルームの扉を開ける鍵が必要になります。事前に管理人さんへご相談していただけるとスムーズにご安置することができます。
- 自宅安置する場合は、ベッドでもよいのでしょうか?
- ベッドで問題ございません。
「ご安置は布団で」というイメージがございますが、最後は生前お使いになっていた、使い慣れたところでお休みになることをおすすめいたします。
- お葬式の日まで数日空いているのですが、大丈夫なのでしょうか?
- お体の状態が変化しないように、私たちスタッフが毎日ドライアイスを交換し、お体の状態を確かめますのでご安心ください。
- お葬式の日までお線香の火を絶やしてはいけないものなのですか?
- ご家族様のお体のことを考え、夜通しでお線香の番をすることは、現在ではあまり行われておりません。日中でも人の目がないときは、防火の観点から火を消しておかれることをおすすめいたします。
- 故人は北枕にしなければいけないのですか?
- 宗派にもよりますが、北枕が一般的です。北枕が不可能な場所では、西へ頭を向け(西枕)ご安置いたします。
神棚のある部屋へ安置を予定していますが、宗教上問題ありませんか?
「神隠し」(神棚を半紙など白いもので一時的に覆う)を行い対応することで、宗教上の問題はなくなります。
- 棺には入れないのですか?
- 納棺の儀式を行うまでは、原則棺に納めません。ただ、ご安置日数が長い時などは、ドライアイスの保冷効果を高めるために、納棺をおすすめすることもあります。
- 故人が好きだったお酒やタバコをお供えしてもいいですか?
- はい、ぜひお供えください。お供え物に決まりはありません。お供えの御飯は、ご家族のお食事の際、ご一緒に交換される方が多いようです。
- 白い布を顔に乗せないといけないのですか?
- 昔からの習わしですが、特に決まりはありません。白布は、亡くなると肌の水分がなくなり乾燥しやすくなるので、乾燥防止の役割もあります。
- 自宅に安置しているときに、故人の体に触れてもいいのですか?
- 生前と同じように接していただくと、故人様も喜ばれます。皮膚の乾燥を防ぐため、顔にアルコールやはっかが含まれていないクリームを塗ってあげるなど、ご家族が故人様に「やってあげたい」と思うことをされるご家族もいらっしゃいます。ただし、感染症の恐れがない場合に限りますので、医者にご確認ください。
- 安置する部屋の温度は何度にすればいいのですか?
- 夏は室温を20度以下に保っていただいたほうがよろしいでしょう。
冬は暖房の使用を控えていただくようお願いしております。
故人様のお肌が乾燥しないよう、加湿器を使われるご家族様もいらっしゃいますが、室内の湿度が高くなれば室温も高まりますので、使用は控えていただいたほうがよろしいでしょう。
- エアコンがない部屋でも、夏場に安置はできますか?
- ドライアイスと一緒に納棺し、外気を遮断することで2日程度のご安置は可能です。
花祭壇について
- なぜ花祭壇を選ぶ方が多いのですか?
- 最近は価値観が多様化し、より明るく華やかに見送りたい、白木祭壇(写真)がイメージに合わないなどの理由で、花祭壇を選ぶ方が増えています。花材、デザイン、色を自由に選べる花祭壇は、ご家族の手で故人様らしさを表現することができます。
またそのお花をお式の最後にお棺に入れることができるため、想いがこもった美しいお見送りができる点でも選ばれております。
- 供花とは何ですか?
- 親しい方やご関係のある方から、お悔やみの気持ちとして贈られるお花です。
デザインを合わせて花祭壇の一部として飾られる場合が多いので、祭壇がより華やかになります。
ご家族・ご親類がお出しするご供花と、会社関係などご家族以外の方々が贈ってくださるご供花があり、前者のご注文はご家族のどなたかに取りまとめていただきます。後者については、訃報連絡書を先方にFAXしていただいた後、葬儀社に直接ご注文いただく方法が一般的です。
- 明るい祭壇にしたい。仏教のお葬式でも、カーネーションなど洋花を使っていいのですか?
- もちろんです。現在は菊だけでなく、色とりどりの洋花を使った華やかな祭壇が人気です。
故人様がお好きだったお色やイメージに合わせて、自由にお花をお選びください。
ただし、おつきあいのある宗教者がいらっしゃる場合は、相談してから執り行います。
- 花祭壇に飾ったお花は自宅に持って帰れますか?
- お持ち帰りになる風習がある地域もございます。
しかし、祭壇に供えたお花は故人様にお手向けする意味合いがあるものなので、一般的にはすべてご出棺の際、お棺の中にお入れします。
お礼状、喪中はがきについて
- お葬式のご案内をしなかった方に、お葬式を終えたことをどうやってお知らせすればよろしいでしょうか?
- はがきでお知らせすることが一般的です。
はがきの手配も私たちでお手伝いさせていただきます。
- 礼状はどのような関係の方に書くのですか?
- 礼状はご葬儀後でお疲れになったご家族様にとっては、大変な作業かも知れません。
こうしたお礼を電話で行なう場合、親しい関係にない方へは失礼にあたることがありますので、礼状を書くことをおすすめいたします。
- どのような種類の礼状があるのですか?
- 【弔電礼状】
弔電をいただいた方には、あいさつの機会を失うこともあるので、礼状にてお礼をします。
【供花(供物)礼状】
遠方からはもちろん、ご供花(お供物)を送っていただいた方には 礼状を出します。
【ご葬儀後に出す死亡通知】
ご葬儀の連絡を遠慮した方や、連絡ができなかった人に死亡通知を出します。
【遠方からの香典・供物に対する礼状】
遠方のご親戚や知人より、ご香典やお供物をいただいた場合、時期をみて礼状とご香典返しをお送りします。この場合、封筒の表書きは「ご挨拶」が適当でしょう。
【年賀欠礼状】
不幸のあった家では、10月~12月上旬に年賀を欠礼する旨を相手に伝えます。
- 喪中はがきは、いつまでに出せばいいですか?
- 11月中にお出しになられたほうがよろしいでしょう。年賀状の準備が早い方は、11月中に済ませられるからです。
11月中旬以降にご葬儀を行われたご家族様には、喪中はがきをお出しにならずに、年明けの1月8日以降に「寒中見舞いはがき」としてお出しすることをお勧めしています。
年賀状を投函された後、喪中はがきを受け取られた方は気を遣われますし、ご葬儀後の手続きに追われてお疲れのご家族様に、ご負担が掛かるからです。
搬送について
- 病院で亡くなったとき、何をすればいいのですか?
- 大切な方が旅立たれた後、看護師が清拭などのお体のご処置(エンゼルケア)を40分から60分ほど施します。ご家族様はその間に、医師から死亡診断書をお受け取りいただき、事前に決めておかれた葬儀社に搬送をご依頼ください。故人様のご処置が終えた後、霊安室へとご移動いただきます。葬儀社の搬送車が到着するまで、お待ちください。
葬儀社に搬送をご依頼される際には、ご安置場所もお伝えください。ご自宅か、ご安置施設か、あらかじめ決めておかれたほうがよろしいでしょう。
病院よっては霊安室がなく、すぐに移動を求められる場合があります。霊安室があっても、お待ちいただける時間は限られているので、納得して依頼できる葬儀社をあらかじめ決めておかれたほうがよろしいでしょう。
また、病衣のまま退院される方が多いので、いつか退院されるときに着せてあげたかったお洋服や、故人様のお気に入りだったお洋服をご用意ください。
なお、病院へのお支払いは後日の場合が多いので、ご確認ください。
- 自宅で亡くなったとき、何をすればいいのですか?
- まずは、救急車か掛かりつけのお医者様をお呼びください。救急車を呼ばれた場合は病院で、医者を呼ばれた場合はご自宅で、死亡診断書をお受け取りいただいた後に、葬儀社へご連絡ください。葬儀社に連絡される際には、どちらにご安置されるのかをお伝えください。ご自宅か、ご安置施設か、あらかじめ決めておかれたほうがよろしいでしょう。
- 深夜、早朝でも搬送はできるのですか?
- 24時間365日対応しております。
- 搬送の車に家族を乗せてもらうことはできますか?
- 2名様までご同乗いただけます。
しかし場合により、ご同乗いただけるのは1名様のみになります。
- 看護師さんから、霊安室から故人を搬送するように言われましたが、誰にお願いすればいいのですか?
- 一般的には葬儀社に依頼し、霊安室に故人様を迎えに来てもらいます。すぐに移動しなければならないので、その場になって慌てることがないよう、事前にご安置場所をご自宅か、ご自宅以外かに 決めておいたほうがよろしいでしょう。
- お医者さんではない白衣を着た人から「今すぐに霊安室から出ないといけないので、うちで搬送します」と言われたのですが、断っても大丈夫ですか?
- はい。断っても大丈夫です。
万が一の時はどうしても慌ててしまい、契約内容もわからないまま依頼することになり、トラブルになるケースもございます。ほとんどの病院などの施設には、提携している葬儀社があり、ご逝去されるとすぐに病室へやって来ますが、この葬儀社に依頼しなければいけないということはございません。
- 病院(警察)から葬儀社を紹介されましたが、断ることはできますか?
- もちろん断ることができます。
病院の多くは提携している葬儀社があり、スタッフは白衣を着ていることがあります。葬儀費用の説明や契約のないまま搬送しようとすることがありますので、ご葬儀をご依頼される葬儀社が決まっている場合は、お断りされた上で葬儀社にご連絡ください。ただし、病室から霊安室までの移動を病院職員の代行をしている場合がありますので、注意が必要です。
- 院内搬送とはなんですか?
- 病室で息を引き取られた故人様を霊安室までお連れすることです。病院と提携した葬儀社のスタッフがご搬送いたしますが、病院外でのご搬送ではないため料金が発生しません。
- 遠距離の地方や海外で逝去した場合、搬送はどうすればいいのですか?
- ご搬送が長距離になると搬送費が高くなることが予想されますので、葬儀社に見積りを依頼されることをおすすめいたします。
緊急事態宣言中のご葬儀について
- この時期お葬式をあげたいけれどどんな感染予防対策をしているのですか?
- 葬儀式場入口にアルコール消毒液を配置し、抗ウイルス対策として来館者全員に手指のアルコール消毒を推奨。葬儀式場内のドアノブ・テーブル・手すりなどの交差汚染の可能性が高い箇所の消毒(次亜塩素酸ナトリウムまたは消毒用エタノールを使用)を徹底。
また入口に非接触体温計を設置し、ご会葬者様には検温をお願いしております。密室空間にならないよう、葬儀式場の入口や窓を開けた状態にし、空気の換気循環 を実施。葬儀式場内では、密集しないよう、座席と座席の間隔を十分に確保。
従業員がマスクを着用した上での打ち合わせの義務付け(なお、従業員には出社前 の検温を実施し、発熱が見られる場合は出勤させておりません)。打ち合わせ時には飛沫防止パーテーションの設置しております。またオンラインでの打ち合わせやメールなどでの書類の送信にも対応しておりますのでご安心ください。
併せて新型コロナウイルスに関する最新情報の全従業員へ徹底研修をしております。
- 来ていただいた方へのお食事はどのように対応したら良いですか?
- 専用の法宴会場ではご家族だけ8名までは対面にならないようソーシャルディスタンスを確保して召し上がれます。
それでもご心配な方はお通夜、告別式後、折詰膳を予めご利用数を把握していただければ、お持ち帰りいただけます。ご利用数確定が難しい場合はグルメギフト(カタログチョイス)のご準備もさせていただきます。
- 参列できない方などへのサービスなど何かありますか?
- 感染症防止の観点から距離と関係ない供養のご案内をしております。
お香典やご供花、ご弔電を出していただいた方へ外出が難しい現在でも弊社がワンストップでお香典返しなどの準備も承ります。
またお葬式やお食事の際のオンライン配信や撮影してのアルバム作成やビデオ作成もなんなりとご相談ください。
また百合ヶ丘家族葬ホールは専用の保冷設備付安置室を併設しておりますので、ご参列にご不安がある方はお式とは別の時間帯を選び密にならずご面会いただけます。
火葬式や家族葬を選ばれた方の中には四九日法要や一周忌と併せ”後日葬”としてお別れの会をご検討の方もいらっしゃいます。
地元に密着した葬祭業店として、これまでご遺族様一人ひとりのご意向に添える丁寧なサービスを心掛けてまいりましたが、今後もそうしたお客様の立場に立ったサービスのあり方を基本姿勢として更なるサービス向上を目指してまいります。
これまで地元で信頼を深めながら葬祭業サービスを営む中、地元の皆様から様々なサービスに関するご質問や、コロナ対策に関するご質問を多数お寄せいただきましたので、主な内容を整理してまとめております。今後葬祭サービスを利用するご予定の方にご参考にしていただけるよう、補足的なマニュアルとして質問・回答形式で分かりやすく解説しています。尚、ここに掲示した内容について更に掘り下げて詳細をお知りになりたい点がございましたら、スタッフまでご連絡いただければ、ご質問内容に丁寧にお応えいたします。